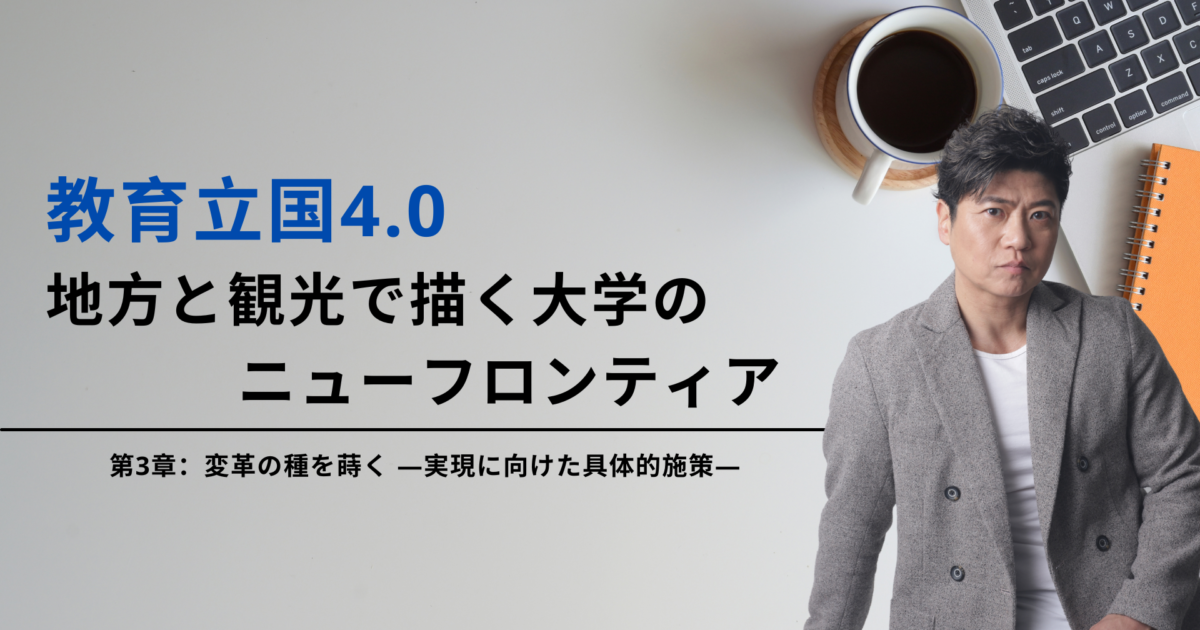第3章:変革の種を蒔く ―実現に向けた具体的施策―
大きな夢を語ることは容易い。しかし、その夢を現実へと育てていくためには、確かな土壌づくりと丹念な手入れが必要となる。さらに重要なのは、その土壌となる「場所」である。本章では、前章で描いた教育改革の青写真を、既存の地域資産、特に寺院という歴史ある教育の場を活用しながら、具体的な施策として展開していく方法を探っていこう。
教育プログラムの改革は、新しい種を蒔くような営みである。観光地域創造学部の設置は、これまでにない新しい学問領域を切り開く試みだ。この学部では、千年の時を超えて受け継がれてきた寺院を、最新の教育施設として活用する。古来より「知」の集積地であった寺院の本堂や講堂は、現代の講義室へと姿を変える。荘厳な雰囲気の中で行われる講義は、学生たちの心に深く刻まれることだろう。
デジタル観光ビジネス学科では、寺院という伝統的な空間の中に最新のテクノロジーを導入する。寺院の持つ文化財としての価値をデジタルアーカイブ化する作業を通じて、学生たちは最新のデジタル技術を実践的に学ぶ。VRやARを活用した寺院案内システムの開発は、伝統とテクノロジーの融合という新しい可能性に挑戦する機会となる。
カリキュラムの刷新も、寺院という環境を最大限に活用する。地域フィールドワークの必修化は、寺院という生きた文化財を教材として活用することで、より深い学びを可能にする。学生たちは、実際の文化財に触れながら、その価値を理解し、保存技術を学び、さらには観光資源としての活用方法を考察する。観光データ分析科目では、参拝者の動向分析から文化財の保存状態のモニタリングまで、幅広いデータを活用した実践的な学習を展開する。
産学連携の推進は、寺院という場所を介して新しい展開を見せる。観光ビッグデータ研究センターを寺院の一角に設置することで、伝統的な空間の中に最先端の研究拠点が誕生する。ここでは、文化財の保存と活用に関する研究から、観光動態の分析まで、幅広い研究活動が展開される。地域観光マーケティング研究所は、寺院を核とした地域の観光戦略を科学的に分析し、効果的な施策を提案する。
人材交流も、寺院という場所性を活かして展開される。実務家教員の積極的採用では、寺院関係者や文化財保護の専門家を教壇に迎える。企業人材の特任教授への登用は、観光産業と文化財保護の架け橋となる人材を育成する。学生の長期インターンシップ制度は、寺院という実践の場で、文化財管理から観光案内まで、幅広いスキルを養う機会となる。
地域貢献の強化は、寺院が本来持っている地域の結節点としての機能を現代に活かす試みである。地域連携センターを寺院内に設置することで、大学と地域の交流の場が自然な形で生まれる。ワンストップ相談窓口の設置により、地域の様々なニーズに柔軟に対応することが可能となる。地域課題解決プラットフォームの構築は、寺院という歴史ある場所で、現代の課題解決に向けた取り組みを展開する。
生涯学習機能の拡充も、寺院という環境を活かして展開される。社会人向け観光ビジネス講座は、実際の寺院を舞台に実践的なケーススタディを行う。オンライン学習プログラムでは、寺院のデジタルコンテンツを活用した遠隔教育を展開する。地域文化継承プログラムでは、寺院に伝わる伝統行事や作法を、次世代に引き継ぐ取り組みが行われる。
これらの施策を実現するためには、いくつかの実務的な課題にも取り組む必要がある。まず、文化財保護と教育活動の両立を図るため、専門家による慎重な検討と計画立案が必要となる。また、Wi-Fi環境の整備やデジタル機器の導入など、現代的な学習環境の整備も欠かせない。さらに、宗教施設としての本来の機能を損なわないよう、利用時間や方法についても配慮が必要だ。
運営面では、寺院関係者と教育機関の緊密な連携体制の構築が重要となる。定期的な協議の場を設け、両者の意向を適切に調整しながら、持続可能な運営モデルを確立していく必要がある。また、文化財の維持管理費用や設備投資の財源確保も重要な課題となる。
このように、寺院を活用した教育改革は、様々な課題を含んでいるものの、その実現可能性は決して低くない。むしろ、すでに存在する歴史的資産を活用することで、新規の施設整備に比べて初期投資を抑えることができる利点もある。
重要なのは、この取り組みが単なる場所の転換ではなく、教育の本質的な転換を促す可能性を秘めているという点だ。寺院という静謐な環境での学び、歴史的な空間での思索、地域との密接な関わりは、現代の教育に新たな次元を加えることができる。
次章では、これらの具体的な施策を展開することで、どのような効果が期待できるのか、さらには、そこから生まれる新たな可能性について検討していこう。
→ 作戦本部株式会社へのお問い合わせはこちらから(https://www.sakusenhonbu.com/#front-contact)