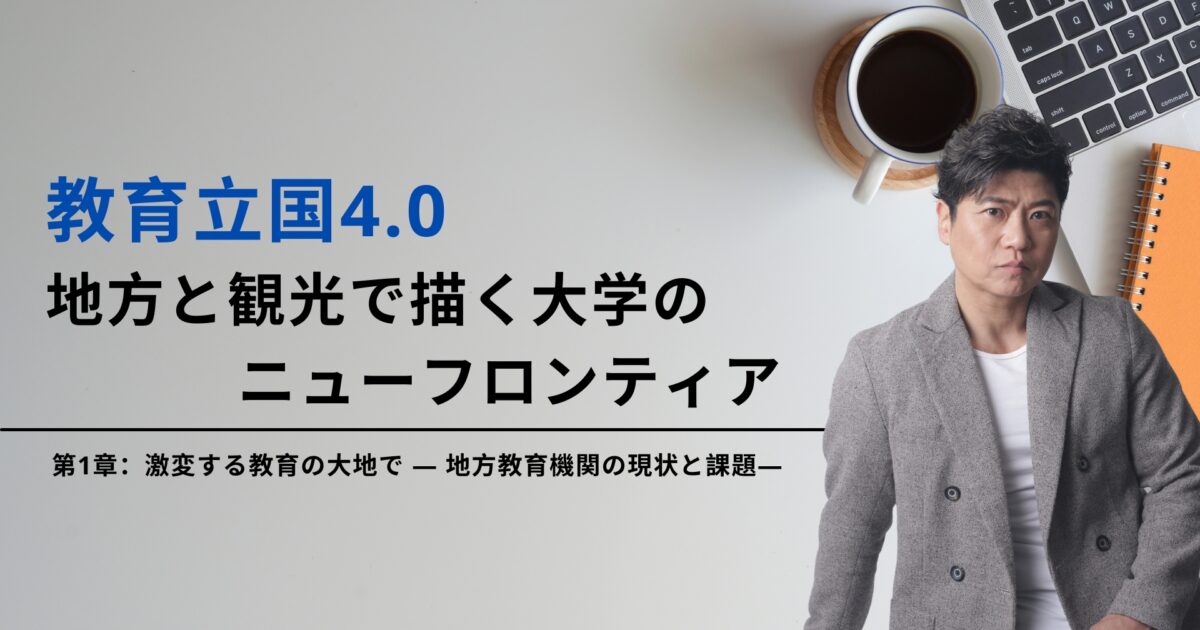第1章:激変する教育の大地で ‐ 地方教育機関の現状と課題 ‐
私も京都にある芸術大学の教員として7年が経過した。
しかし、その美しい風景とは裏腹に、多くの地方大学は深刻な危機に直面している。かつて若者たちの熱気で溢れていた講義室には、空席が目立つようになった。まるで干ばつに見舞われた大地のように、18歳人口という貴重な水源が年々減少していく中で、地方の教育機関は生き残りをかけた苦闘を続けている。
2040年、日本の18歳人口は約88万人にまで減少すると予測されている。2020年の約117万人と比較すると、わずか20年で約25%もの減少だ。この変化は、静かに進行する地殻変動のように、日本の教育界全体を揺るがしている。特に地方の私立大学では、すでにその影響が顕著に表れ始めている。約4割の私立大学が定員割れという状況は、教育という豊かな土壌が徐々にやせ細っていく警告であると言えよう。
都市部への学生流出は、まるで強い磁石に引き寄せられるように続いている。「東京一極集中」という言葉は、もはや社会現象を表す単なる表現ではなく、地方大学の存続を脅かす重大な課題となっている。都市部の大学が巨大な渦のように若者を吸い込んでいく中で、地方大学は独自の魅力を見出し、新たな価値を創造していくことを求められている。
財政面での課題も深刻さを増している。運営費交付金の継続的な削減は、教育機関という樹木から養分を奪っていくようなものだ。基礎的な教育・研究活動という根や幹が細る中で、新しい枝葉を伸ばすための投資は困難を極めている。施設・設備の老朽化は進み、専任教員の確保もままならない状況は、まさに負のスパイラルと言えよう。
地域との連携不足も見過ごせない問題である。大学は地域という大きな生態系の中で生きている生命体だ。しかし、多くの場合、地域のニーズと大学のシーズは、まるで異なる周波数で振動する波のように、うまく共鳴できていない。産学連携の取り組みは限定的で、地域社会への貢献度も見えにくい状況が続いている。
この状況は、地方創生という大きな課題とも密接に結びついている。2045年までに地方圏の人口は2015年比で約2割減少すると予測されており、この人口減少は寒波のように地域経済を凍えさせている。若年層の流出は、地域の活力を奪い、商店街の衰退や公共サービスの縮小という形で、その影響は目に見える形で現れている。
しかし、この危機的状況の中にも、新たな可能性の芽は確実に育っている。その一つが観光産業だ。コロナ禍からの回復に伴う訪日外国人の増加は、まるで長い冬の後の春の訪れのように、新たな希望をもたらしている。特に注目すべきは、観光需要の質的変化である。単なる観光地めぐりから、体験型・学習型観光へとシフトする観光客の志向は、教育機関にとって新たな可能性を示唆している。
地域固有の文化や歴史への関心の高まりは、まさに地方大学が持つ知的資源を活かせる機会となりうる。また、ワーケーションの普及や教育観光(エデュツーリズム)の台頭、サステナブルツーリズムへの注目は、教育機関が新たな役割を果たせる可能性を示している。
これらの変化は、地方の教育機関に突きつけられた課題であると同時に、大きな転換の機会でもある。荒れ地のように見える現状も、適切な施策という水と栄養を与えることで、豊かな実りをもたらす畑に変えることができるかもしれない。
次章では、このような現状認識を踏まえた上で、具体的にどのような教育改革が必要とされているのか、その方向性と可能性について詳しく見ていくことにしよう。
→ 作戦本部株式会社へのお問い合わせはこちらから(https://www.sakusenhonbu.com/#front-contact)